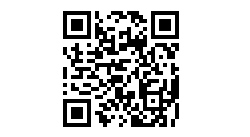7月 1 2016
NewsLetter 2016年7月号
「歯周基本治療」と「歯周外科治療」
歯周病は、歯ぐきだけに炎症があるごく軽度のものから、歯を支える骨が大きく失われた重度のものまで、その症状に幅があります。症状は違っても、歯周病という病気の治療する際の目標は共通です。炎症の原因である細菌(プラーク)を取り除くこと、そしてそのきれいな状態を維持することです。
そのために患者さんに、まず受けていただくのが「歯周基本治療」です。
歯周基本治療の主な内容は、細菌の巣である歯石の除去(スケーリング)と、プラーク(歯垢)除去に必要なセルフケアを上達させるためのブラッシング指導です。
「歯周外科治療」は、歯周基本治療だけでは炎症が止まらない場合に行う、外科的な歯周治療です。
深い歯周ポケットの中に残った歯石を取り除き、深い歯周ポケットを浅くするため歯ぐきを切開して、直接歯根や骨にアプローチする治療です。
成人の8割以上のお口の中で、歯周病が進行しているといわれています。歯周基本治療や歯周外科治療の必要ない方は、まず希だといって良いのが現状です。早期発見するほど治療に有利ですので、定期的に歯科医院へおいでいただき、普段から予防を心がけていきましょう。
いの歯科医院 歯科衛生士 山川まり子
参考文献:nico/2016.03
お口の中に異変を感じたら
舌がヒリヒリしたり、歯ぐきに水疱や潰瘍ができたり、ほっぺを噛んだ覚えがないのに血腫ができたりすることがありませんか?
お口の中もからだの一部です。お口の中に全身疾患の症状が現れることは、めずらしいことではありません。
歯科医院で原因がわからない粘膜疾患は、放っておかずに内科や皮膚科のかかりつけ医相談するか、歯科医院で大学病院などの口腔外科を紹介してもらいましょう。
(nico 2016.03より)












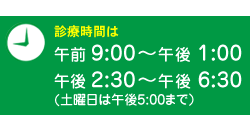
 →地図を拡大表示
→地図を拡大表示