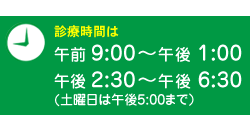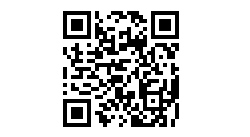6月 1 2015
NewsLetter 2015年6月号
怖がらないで顎関節症!
顎関節症とは、顎関節やその周りにある筋肉が口を動かすと痛む、関節音がする、口が開かない、動かしにくいといった病気をいいます。
顎関節症の原因として考えられているものには患者さん自身の顎の弱さから、打撲や外傷、肉離れや捻挫の他、ストレスや噛みしめ、歯ぎしり、日常のちょっとしたクセ、仕事などがあり、これらは多岐にわたります。
「噛み合わせの不良」もその中に含まれていますが、あくまでも様々ある中の「ひとつ」でしかありません。様々な病因が積み上がって、患者さんの耐性を越えると顎関節症が発症します。
顎関節症を発症、憎悪させる原因を減らすために、日常生活で何気なく行っているクセや習慣を見直しましょう。背筋を伸ばす、口を閉じている時は上下の歯を離す、睡眠を充分取る、仕事の合間に休憩する、うつぶせで読書をしない、頬杖をやめる、電話の肩挟みをやめる、硬い食べ物は控える。
気づいて改善していくと症状がグッと楽になります。
いの歯科医院 歯科衛生士 山川まり子
参考文献:nico/2015.02
顔の筋肉とシワの関係って?
食事を短時間で済ませたり、軟らかい食べ物ばかり食べていると、顔の筋肉が衰え、頬がたるんでほうれい線が目立ち、口角が下がってきてしまいます。
すると、全体的に老けた顔に見えてしまう事もあります。
顔の筋肉を衰えさせず、若々しい顔でいるために大切な事は、「良く噛むこと」「よく歌うこと」「よくしゃべること」です。
食事の内容に気を配り、良く噛んでゆっくり食事を楽しむ余裕も必要です。表情豊かに歌ったり、大きく口を開けて笑うことも効果がありそうです。
(nico 2015.02より)